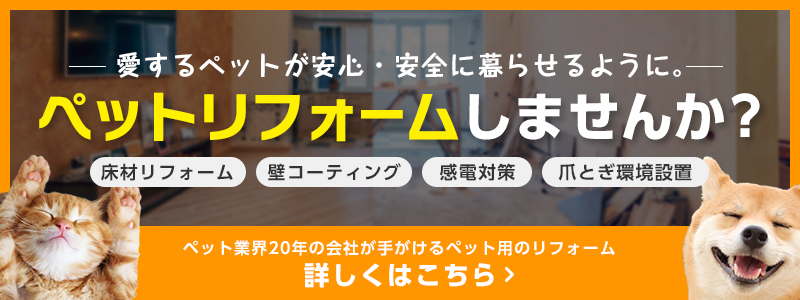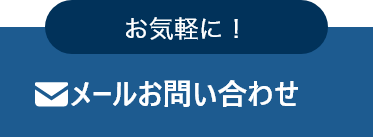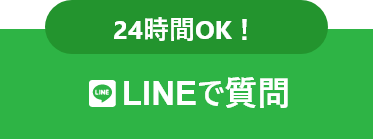投稿日:2023.09.16/更新日:2024.07.19
猫が脱走したとき帰ってくる確率や脱走しないための対策を紹介

猫が頻繁に家から脱走し、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。猫が脱走すると交通事故に遭っているのではないか、誘拐されているのではないか、外敵に襲われていないかなど、さまざまな不安が頭をよぎるものです。
ある程度の時間が経てば帰ってくるケースもありますが、自ら帰ってくる確率はどの程度なのでしょうか。また、脱走を防ぐためにできる工夫もあわせて紹介します。
猫が脱走してしまう原因や理由

猫を飼っていると、ちょっとした隙をついて家の外へ脱走してしまうことがあります。なぜ猫はこのような行動をとるのでしょうか。考えられる原因や理由をいくつか紹介しましょう。
大きな物音や身の危険を感じた
猫は家のなかでリラックスして過ごすことが好きです。しかし、そのような環境下でいきなり大きな物音がすると、外敵が襲ってきたと勘違いし安全なところに避難しようとします。
特にインターホンが鳴ったときや玄関を開けたとき、ものを落としたときなどにそういった行動が見られます。
気まぐれ・興味本位
猫はもともと気まぐれな性格の動物として知られており、気まぐれで家の外に脱走することがあります。
また、窓から外の様子を見ているときに、興味をそそるものが目に入るとそれに釣られて脱走を図ることもあるでしょう。
異性を探すため
発情期を迎えたときも猫は脱走を図ることがあります。
去勢や避妊手術をしていない猫は発情期になると異性を求めることが多く、脱走のリスクが高まる傾向にあります。
環境の変化でのストレス
猫は環境の変化に敏感であり、引っ越しや新しい家具の導入、新しいペットの追加などがストレスの原因となることがあります。
これにより、猫は脱走を試みることがあります。環境の変化を最小限に抑え、猫が安心できるスペースを確保することが重要です。
関連記事:家の猫が脱走?好奇心旺盛な猫の脱走防止の為にできる玄関対策!
猫が脱走したときに帰ってくる確率
猫は自分の住処に帰ってくる帰巣本能が備わっており、家の外に出たとしても自力で帰ってこられる可能性は十分にあります。
ただし、犬や鳥ほど帰巣本能が高いというわけではなく、室内飼いの猫の場合が自力で帰ってこられる範囲は半径50m程度とされています。
また、一般的に脱走してから日数が経過するほど帰ってくる確率が低くなるとされており、1週間以内では30〜40%、1カ月以上が経過すると10%ほどの確率しか見込めなくなるとされています。
猫が家から脱走する行為は決して珍しいものではありませんが、長期間にわたって家に帰ってこない場合には捜索する必要があるでしょう。
関連記事:猫がキッチンに侵入するのはなぜ?防止対策や工夫例をご紹介
脱走した猫の探し方

脱走した猫はどのように捜索をすれば良いのでしょうか。「これをすれば必ず見つかる」といった方法はありませんが、発見できる確率を上げられる方法はあります。
保健所・動物病院・警察への問い合わせ
脱走した猫に首輪などが装着されており、明らかに飼い猫であると判別できる場合、誰かが保護してくれている可能性があります。
一般的に迷子のペットは誰かが保護した後に保健所や動物病院などへ連れてこられるケースが多いことから、まずは問い合わせてみましょう。また、場合によっては警察や交番に届けられている可能性もあるため、念のため確認してみることが大切です。
猫が隠れそうな場所を探す
猫はもともと高い場所や暗く狭い場所を好む動物です。そのため外壁や塀の上、空き地や公園の隅、建物の隙間、側溝の内部などを中心に捜索してみましょう。
また、脱走すると遠くに逃げてしまったのではないかと不安になる方も多いですが、意外と自宅の近くに潜んでいるケースも多いものです。
たとえば、古い住宅であれば軒下や床下の隙間、車の下、物置の影、門扉の裏などを入念に捜索してみると早く見つかるかもしれません。
早朝または日没後に探す
昼間の間は多くの人通りや車の往来があり、警戒心を抱く猫も少なくありません。また、猫は早朝や日没後に活発に行動する特性があることから、捜索する場合にはこれらの時間帯を選んでみましょう。
その際、猫が好きなフードやおやつ、おもちゃなどを準備しておくのがおすすめです。
関連記事:猫を飼う前に知っておくべき事7選|準備するものや費用を解説!
脱走した猫が見つからないときの対処法

飼い主が自力で周辺を捜索してみたものの、どうしても見つからないというケースもあるでしょう。自宅周辺から遠く離れた場所にまで逃げている可能性がありますが、このような場合にはどういった対処法が効果的なのでしょうか。
チラシやポスターでの呼びかけ
脱走した猫の名前や特徴、写真などを掲載したチラシやポスターを作成し、ポスティングや近所のお店・自治体の掲示板などに掲示を依頼する方法があります。
半径数百メートルの範囲にいる可能性が高いことから、近所の人の協力を得ることで早い段階で見つけられるかもしれません。
SNSの活用
チラシやポスターといったアナログな方法と合わせて、SNSで多くのユーザーに拡散してもらう方法も有効です。
チラシやポスターを作成・印刷する手間もなく、瞬時に多くのユーザーに向けて発信できる点は大きなメリットといえます。
ペット探偵への依頼
長期間にわたって自力での捜索をしているものの、どうしても見つけられないという場合には、最終手段としてペット探偵に依頼する方法があります。
ペット探偵とはその名の通り、脱走したペットの居場所を探し出し、捜索・捕獲するというサービスです。
1日あたり数万円程度の費用がかかりますが、飼い主の力だけではお手上げという場合に役立つでしょう。
関連記事:猫に一人遊びが必要な理由や飽きないおすすめのおもちゃを紹介!
猫が脱走しないための対策

猫が脱走を図る理由はさまざまですが、脱走のリスクを低減するためには適切な環境作りや脱走防止アイテムなどが効果的です。
ドアや窓は閉めておく
基本的な脱走対策として有効なのは、ドアや窓は開けっ放しにせず閉めておくことです。
猫は頭が通る隙間なら身体も通り抜けることができるため、わずかな隙間が開いていると、そこから脱走を図られてしまいます。
猫と触れ合う時間をつくる
猫がストレスを感じていると、刺激を求め脱走を図ることがあります。このような行動をとらせないようにするためには、飼い主が猫と触れ合う時間を確保し、遊んであげることでストレスを発散させることが求められるでしょう。
ケージの活用
活発で好奇心が旺盛な猫は、ちょっとした隙をついて脱走を図ることがあります。
特に脱走のリスクが高い場合には、猫専用のケージを設置する方法も有効です。
高さのある大きめのケージであれば、ストレスに感じることもなく快適に過ごせるでしょう。
ペットリノベーション
そもそも猫が脱走しやすい間取りや構造になっている家も少なくありません。
そのような場合には玄関を二重扉にしたり、リビングから廊下への間に侵入防止の柵を設けたりするなど、リノベーションを行うことも検討してみましょう。
ペットショップやホームセンターなどでは、簡単に設置できる柵も販売されています。
キャットタワーなどの家具でのストレス解消
キャットタワーやキャットウォークを設置することで、猫に遊びやリラックスのための専用スペースを用意することができます。
これにより、猫のストレスを軽減し、脱走を防ぐことができます。
テイストは猫の脱走防止に効果のあるペットリノベーションが可能
二重扉や柵の設置といった大掛かりな工事は、リノベーション業者へ依頼するケースが多いものです。猫の脱走を防止するという目的を果たすのであれば、ペットリノベーションを得意とする専門業者へ相談してみましょう。
なかでもテイストは多くのペットリノベーションを手掛けてきた実績とノウハウがあり、猫の脱走を防止するための住宅設備や間取りの変更に対応できます。
二重扉や柵の設置はもちろん、それに伴う床や天井の補強工事、ペット専用ルームのリノベーションなど予算に応じた相談が可能です。
まとめ
猫が脱走した場合、1週間以内であれば40%程度の確率で帰ってくる可能性はありますが、1カ月以上になると10%程度にまで低下します。
脱走した猫は意外と自宅の近くに潜んでいる可能性も高いため、まずは猫が隠れそうな場所を重点的に探してみましょう。
同時に、猫が脱走しないような工夫も必要であり、そのための具体策としてペットリノベーションも検討してみてはいかがでしょうか。